迷チョウ探し
3連休も最終日。前日は幼稚園の運動会だったので、
やっと(?)「迷チョウ探し」に遠出ができました![]()
![]()
出る時刻が遅かったので、期待はできませんでしたが、
向かったのは大野岳。(左に池田湖、右に開聞岳が見えます)
頂上付近で、採集仲間のご家族とご対面。
皆さん、考えることは同じです![]()
去年も9月にそこを訪れたのですが、その時もお会いしました。
台風後ということで、迷チョウが留まるポイントとして有名な場所です。
そのご家族以外にも、何組ものハンターの方々が訪れていたそうです。
結局、迷チョウというほどのチョウには出会えませんでしたが、
パパがアサギマダラ(オス)をネットイン。ノーマーキングでした。
しかし、全体的に全然虫がいません…![]()
チョウの代わりに、可愛らしい野の花を見つけました。
名前は判りませんが、大野岳のあちこちにひっそりと咲いていました![]()
帰りに千貫平にも寄りましたが、
また別の採集家族にお会いし、情報交換![]()
やっぱり「いないね~」という結論でした![]()
来週、また「虫っこクラブ」の活動で、迷チョウ探しがありますが、
その時こそ、何かまだ出会ったことのないチョウに会ってみたいです![]()




















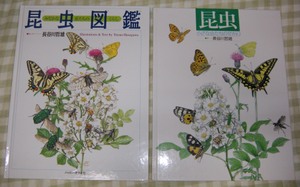


最近のコメント